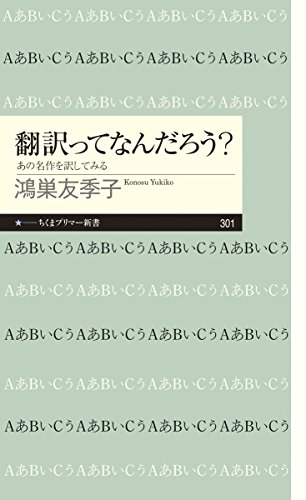小説を読んでいて、途中で毛糸の色が変わっていたらどう思うだろう? あるいは、本棚にジャムや食器が入っていたら? 建物があり得ないような壊れ方をしていたら? ヒロインの話す英語が完璧すぎたら? 愛する女性の名を口にしない男たちがいたら? そこからどんなことが読みとれるだろうか?
『赤毛のアン』『ライ麦畑でつかまえて』『高慢と偏見』『情事の終り』『風と共に去りぬ』……。誰もが知る名作十作の、見落としがちだが重要なツボをワークショップ形式で探ろうというのが、本書『翻訳ってなんだろう? あの名作を訳してみる』だ。どうやって探るかというと、翻訳という作業を通して。
翻訳は体を張った読書だ! と、翻訳の仕事を始めて三十年経つ最近つくづく感じる。実は仕事を始めて十数年は、翻訳者とは作者の代理だと思って気張っていた。それが、なにか憑き物が落ちたように変わったのは、ブロンテの『嵐が丘』で、初めて古典新訳を経験してからかもしれない。日本で昭和初期から営々と築かれてきた『嵐が丘』の読みの下地、無数の解釈と訳文、いや、世界に目を広げれば、そこにはもう目眩のするような、Wuthering Heightsの“翻訳”の茫洋たる大海が広がっている。その大海原に自分は一滴の小さな雫となって入っていくだけだと気づいた。要するに、翻訳者も読者のひとりであり、翻訳とはその大部分が「読む」ことだ、と。
しかし翻訳者の場合、精密に読むだけではすまされない。純粋な読者と違うところは、そのことばの当事者となる点だ。
「〇〇文学賞受賞というので手にとったが、ダラダラ書いてあるばかりで疲れた」とか「男がある日目覚めたら虫になっていたなんてあり得ないので、理解できませんでした」なんて、巷のブックレビュウには書かれておりましょう。“批評者”というのは、こうして他者の作品を認識し評する(その評が的確かどうかは別として)。翻訳者もそこまでは同じだけれど、しかし訳文に、「ダラダラ書いてあって退屈な小説です」とか「人間が虫になるところが変です」とか他人事のように書くわけにはいかない。本当にその文章がダラダラしているなら、訳文も身をもってダラダラさせなくてはならないし、本当に理解不能の内容なら、そのわけのわからなさを当事者として言語化する必要がある。
『翻訳ってなんだろう?』は実際の翻訳講座などを下敷きに書かれ、読者のみなさんにも「ことばの当事者」となってもらうべく、一章ごとに違う名作の一部を課題文としてお出ししている。ちょっとしたルールを設けることもある。第三章の『嵐が丘』では、「キャサリンとヒースクリフの既成イメージからなるべく遠い人称代名詞を選んで訳してください」とお願いした。講座では、「おいら」「うち」「わて」「あんさん」など実にさまざまな人称代名詞が登場し、世紀の恋愛悲劇がナニワの夫婦漫才みたいに見えてきたりした。また、第五章の『ライ麦畑でつかまえて』では、「ホールデン少年のささいな口癖をいちいち訳出してください」とお願いした。そうすることで少年の心のなにが見えてくるだろう? 第四章のE・A・ポー『アッシャー家の崩壊』では、「なるべく原文の語順どおりに訳してください」。この作家ならではの「非効率的な文体」にとことんつきあうことで、ポーの文章はなぜあんなに怖いのか、その恐怖の源泉を探っていく。
わたし自身、翻訳してみて初めて気づくことが実にたくさんあった。英語を英語のまま理解して楽しむ原典講読は、ある意味、読書の最高峰だろう。その一方、異言語である英語をあえて母語の日本語にくぐらせ、さらに自分のことばとして見知らぬ他者に伝える翻訳を通して得られる深い味わいも、また得難いものだと思う。
これを学習目的の「訳読」ではなく、「翻訳読書」と名づけてみた。訳してわかる名作のヒミツ、翻訳のヒミツ。どうぞ、あなたも体験してみてください。

PR誌「ちくま」より、6月刊 『翻訳ってなんだろう? あの名作を訳してみる』(鴻巣友季子著、ちくまプリマー新書)の新刊紹介を公開します。翻訳家・鴻巣友季子さんが、自身の翻訳家としてのキャリアを振り返りつつ、、翻訳をしながらより深い読書をする「翻訳読書」の楽しみについて語る、魅力あふれるエッセイです。ぜひご堪能ください。