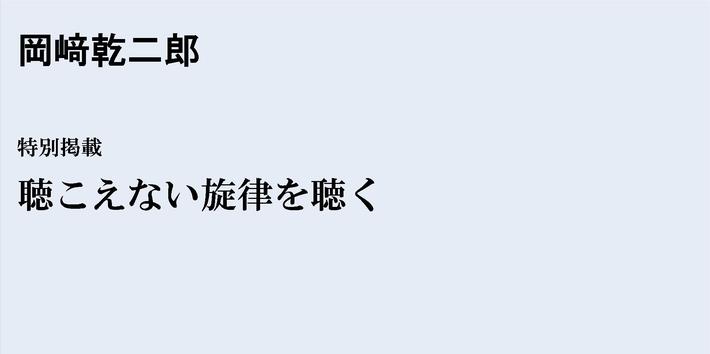4
椅子に座っている少女がいる。その少女はつま先だけ地面につけ、踵を浮かせている。隣にはもうひとつ椅子があり、そこには誰も座っていない。少女は膝の上にのせた両手を握りしめ、正面を見つめている。少女は、彼女を見下ろすように見ている、わたしたちを見てはいない。少女の左肩には小鳥がとまっている。――
──ある彫刻作品を見えたまま気づくところを記述したものである。この彫刻を前もった説明なしに、見る人が理解できることはなんだろう。誰も座っていない椅子は、そこに座っていた誰かが立ち去って、その誰かが不在になっていると想像させる。さらに、その不在の椅子はこの彫刻をいま見ているわたしたちが座ることもできること、座ってみることを促しているようにも感じられる。少女の視線は少女を見下ろすわたしたちを見てはいない(たとえ、わたしたち鑑賞者が正面から彼女を見つめても、当然のことながら彼女は気づく様子はない)。だから、わたしたちの立場はかつて椅子に座っていたはずの不在の誰かと同じく、少女にとって不在の存在だろう。つまりこの像を見ているわたしたちは少女にとって幽霊のように、いわば死者の立場になって彼女を見ていることになる。しかし、彼女の肩にとまる小鳥の像は(この彫刻が野外に置かれたとき、はっきりとわかるだろう)わたしたちにとっても少女にとっても、そうではない。現実の小鳥たちがたえず入れ替わるように集まって、すでに少女の肩に乗った、この小鳥の像と同じように、少女の肩(あるいは頭や膝)にとまって、にぎやかにさえずるに決まっているからである。わたしたちはそれを見ているし、少女が肩にのる小鳥の像と同様に、いままた訪れる小鳥のかすかな重みを感じていることはわたしたちにも感じられる。
すでに明らかなようにいま記した少女の像は、冒頭で記したレキュトスとも通じる、日常の時間と空間を超えた外へと、わたしたちを連れ出してくれる開かれた構造を構成している。この少女の像がひとり、とり残された(あるいは少女の像が連れてこられ置き去りにされた)場所は、たとえそのまわりを多くの人にとり囲まれたとしても孤立し世界から離れて感じられる。少女のいる現実からは、彼女をとりまく人々は別の世界にある。レキュトスに描かれた少女と同じように彼女の足の踵が地面から浮いているのは、この少女像の少女もレキュトスの少女と同じく自分の置かれた世界から離れたいと感じていることの表れかもしれない。さらに観察すれば座る少女の足元からは影を象ったような形が伸び、舗石に嵌めこまれている。これが影であるならば見ているわたしたちには影がなく(ピーターパンと同じように)わたしたちが少女の世界にとって別の世界にいる、という感覚はますます強くなる。けれどこの影はこの少女のものなのだろうか。すでに少女の踵は浮き、(影だけを地面に残し)この影から離れようとしているのだから。――
結局のところ、わたしたちが強く自覚させられるのは、わたしたちが実際に見たり聴いたりしている、この煩わしい現実の世界(少女が連れてこられて置かれている)とは離れた(直接には見ることのできない)どこの場所にも属さない別の世界の可能性である。現実の知覚においては見えない、不在=ネガティブで存在しない場所こそが強く喚起される。わたしたちはそのネガティブな場所、どこでもない場所へ移行する能力=ネガティブ・ケイパビリティをわたしたちもまた持っていることを自覚するのである。この少女の像には『平和の少女像』(キム・ソギョン、キム・ウンソン作)という題名がつけられている。