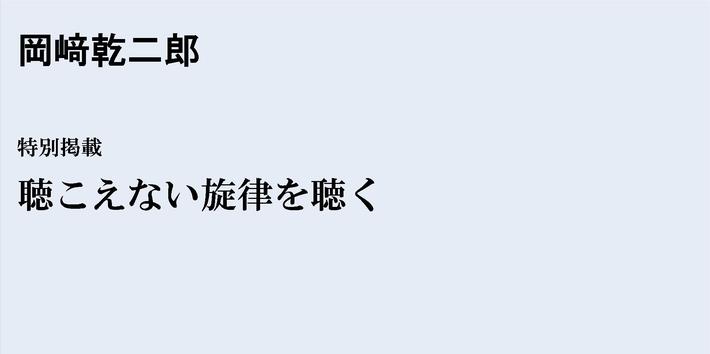6
芸術作品が開く可能性は、いま、この場所、この現在に属する鑑賞者たちからのみ同意を受け取ることにあるわけではない。現在という限定された時と場所(それは政治によって分割され統治された場所である)に属す人間からは排除されたすべての存在(それは死者たちを含むあらゆる人間、のみならず、動物たち、鳥たち、魚たち、地上に存在するすべて)に開かれた場所、いいかえればこの世には位置づけられない、不在の場所を開示する力によってである。
しかし考えてみれば、これはMedium(この場には不在のものと交流する)という語源に遡って、メディアとよばれるものすべてに期待される力である(マーシャル・マクルーハンは、メディアは、不在のものに開かれたクールなものであるとき、はじめてその力を発揮すると指摘していた)。
たとえば、藤幡正樹が香港という街を舞台に構築した『BeHere』というプロジェクトは、現実を拡張するのではなく、むしろ現在ある場所を〈不在の場所〉へと開放する。現在の閉じた世界を開放できるのは、現実においてネガティブだとみなされる場の能産性なのだ。これこそがMedium の本来ある力、メディアアートの真髄だろう。
香港の街角で市民たち自身がかつて撮影(戦後から70 年代まで)したスナップショットを3次元データで再現し、AR 技術で、撮影されたもともとの街中の現場にデータとして埋め込んでいく。かつてそこに過ごし、笑い、語り合った人々の姿はもはや現実の場面では見えないが、『BeHere』のアプリ(スマフォにダウンロードできる)を通せば、いまだ街のあらゆる場所にその人々が存在しつづけていることがわかる。かつて存在した、すでに不在になったはずの人々と一緒に記念写真を撮ることさえできるのである(が、ここでも、別の世界に属す人々の視線が出会うことはない)。――

が、この装置の核心は、こうした経験が与える奇妙な感覚にある。すなわち、ひとたび、この装置を経験すると香港の街はもうかつてと同じように見えることはない。それは不可逆で絶対的な経験を与える。街はそこに不在である人々たちによっていまだ賑わい、逆さまにいえば、いままで実際に香港の街にいて、この街を現実として見ていたはずの自分たちもまた その不在の人々ともに、香港の街には本当はいなかったように感じられる。すなわち香港には誰もいない/すべての者がいまだいる。背理に感じられるがそうではない。正確にいえば、むしろ自分たちの不在性が強く感じられ、それを受け入れたとき、そのとき、香港の街は現実の何ものにも支配されない、侵入されない別の場所として永遠に存在しつづけていることが確信されるのである。その決して打ち消すことのできない権利を、そのわたしたちが持ち続けるべき場所の理をこの作品は、不可逆な確信として与えてくれる。
聴こえない旋律=音楽、そのいかなる限定をも超えて広がりをもった響きは、もはや決して消すことはできないだろう。わたしたちはそれを聴くことができる、わたしたちはもはや(ずっと)不在であったがゆえに、永遠に強固な場所にいるのだ。小鳥の鳴き声、蝉の鳴き声が止むことはないだろう。それは何千年も前から(さまざまな政治的な対立をものりこえて)、ずっと(いまも)聴こえている、聴くことができる。この不在の場所で。
*この小文はもともと香港のHKACT Osage Art Foundationの出版物「Art in the 21st century: Reflections and Provocations」のために書きはじめたものです。機会を頂いたHKACTと藤幡正樹さんに感謝いたします。