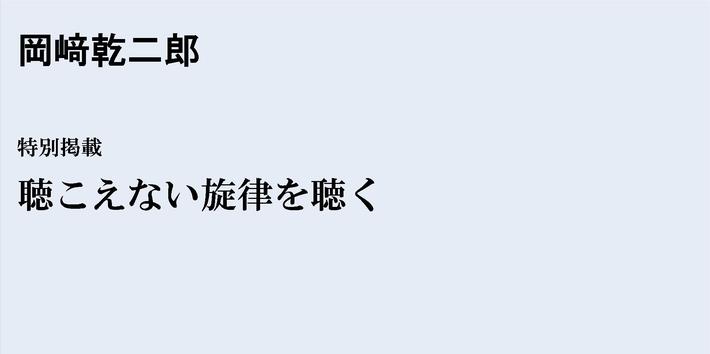2
知られているように《死者と生者の対話》は、ギリシャの壷絵の主要な主題だった。そこで示される視線のすれちがいはそのまま二つの別の世界の交差と乖離に対応されている。ここに描かれている人々は、互いの存在を意識しつつも触れ合うことができない別の世界にいる。二人の存在が現実的には乖離しつつも、《たましい》においてかろうじて交流している様子は、この壷の絵を注意深く見ているだけで感じられる。そのことは2500年近くも時を隔てた、また場所も文化もまったく違う、2019 年の日本で見ても感じられるということである。
「耳に聴こえる旋律はうるわしい、けれど聴こえない旋律はもっとうるわしい」という一節で名高い、ジョン・キーツ(1795-1821) の『ギリシャの壺のオード』は、こうした主題を共有するギリシャの壺の一つを題材にして書かれている。
耳に聴こえる旋律はうるわしい、けれど聴こえない旋律は
もっとうるわしい。だから、やさしい笛よ 奏でつづけなさい
耳で感じられるものではないけれど、はるかに慕わしい、
音をもたない小曲を、響かせてほしい、たましいに。
木陰に いる青年よ きみは その歌を忘れることは
できない。木々の すべての葉が散るわけではないように
おそれなく恋する青年よ きみは決してキスにいたることはない
勝利のゴールまぢかまで近づいても。でも悲しむことはない
乙女のすがたは消えることなく、いつまでも若く
いつまでもきみは愛しつづけ、乙女も永遠に美しい
(ジョン・キーツ『ギリシャの壺へのオード』、拙訳 )
「聞こえない旋律」とキーツがこの詩を通して語っているのは──わたしたちがもつ「現在という時」の意識は、わたしたちの感覚すなわち視覚や聴覚によって裏づけられているけれど、感覚から導かれる旋律=音楽は、結局はその時間や空間に位置づけられないものだということである。だからそれは消えることはない。もともと日常的な時間に属していないのだから。
感覚器官として耳は、いま、ここという現在の時と空間の一点で捉えた音だけを知覚することができる。が、それが音楽=旋律として自覚されたとき、その音楽=旋律は現在という瞬間を超えた(最低でも前後の時間の)広がりをもち、空間としても一点の位置を超えた広がりをもって把握される。つまり音楽=旋律は特定の時間や場所を超えており、だから感覚器官としての耳で直接、聴くことはできない。その、耳では直接聴くことのできない旋律の響きも、それを捉える=聴くことのできる《たましい》も、日常の時間や空間を離れた外にある。いいかえれば音楽=旋律は日常の時間や空間に位置づけられない、それ自身の固有の場を備え、そこにあると認識される。「音をもたない小曲を響かせてほしい、たましいに」とキーツがこの詩のなかで語るのはそういう意味だろう。音楽=旋律は《たましい》とともに、いつまでも時間の外に留まる。
3
音楽=旋律は、耳という感覚がとらえることのできる現在という時間、場所に属す音ではなく、その現在から離れた《たましい》の中に響いている。音楽=旋律はその意味で現世から疎外されている(現在という時間からも場所からも)。しかしこの疎外、つまり直接には聴こえない、見ることができない、という不能性こそが音楽ひいては芸術を理解する能力、何かと共感する能力の源になっている──キーツはそれを、ネガティブ・ケイパビリティと呼ぶ(ネガティブ・ケイパビリティnegative capabilityは〈消極能力〉と訳されているが、意味としてはむしろ〈負にとどまる能力〉だろう)。
えらい仕事を仕遂げた人を構成する性質、シェイクスピアが多量にもっていた性質──私が消極能力という性質のことです。この消極能力というのは、人が、事實や理性などをいらだたしく追求しないで、不確定、神秘、疑惑の状態にとどまっていられるときを言うのです。
(『キーツ書簡集』、佐藤清訳)
レキュトスの壷絵に戻せば、その絵の中で死者と生者を隔てていたものは、それぞれの時間に縛りつけられた感覚だった。少女は聴くことができても見ることはできない、青年は見ることができても聴くことができない。それが少女と青年が此岸、彼岸という二つの場所に隔てられていることを示す。同じ時間と空間にあるものしか人は見ることができないし聴くことができない。だから二人は別の世界に隔てられている。
ネガティブ・ケイパビリティとはこの《できない》という否定性を受け入れる能力である。それを受け入れたとき《たましい》は直接的な感覚(そして、それが位置する特定の場)から離れた音楽=旋律を奏でることができ、共振させることができる。
キーツの論を敷衍させれば、それぞれが、あらかじめ共有されていると信じられた場から疎外されていること、つまりそれぞれ固有の《できない》という否定的条件、お互いの不可能性を認めたとき、その否定性から、はじめて共感能力は作動し共感が可能になる、ということもできる。そしてその共感はもはや、どこの場にも属さない。
相容れない隔たった場所とは生者と死者、彼岸と此岸に限らない。敵と味方、白か黒か、正しいか誤りか、相対するだけで決して解決できない論争、紛争、対立のすべて、これら私たちの生に膠着する煩わしいだけの問題を乗り超える可能性を、キーツはネガティブ・ケイパビリティに見出そうとしていたのだ。