「ミステリアスな文の集団、この集団はなんなのだ」
ラグーナとはイタリア語で「干潟」を意味する。干潟には多様な生物が棲み、潮の流れと生物の力が海水を浄化する。干潟のように一見不毛と思われる場所を照射したい。社名には創業者たちのそんな決意が込められている。
ラグーナ出版が設立されたのは、鹿児島の精神科病院、尾辻病院で働く精神保健福祉士の川畑善博と、統合失調症で入院していた竜人(筆名)の出会いがきっかけだ。
2005年の2月のこと。川畑がタバコを吸うため喫煙所に行くと、入院中の患者が通りかかった。いつも朝から晩までぐるぐると廊下を歩いている竜人だった。ある日、彼が川畑に話しかけた。
「遺書のつもりで書きました。読んでくれませんか」
川畑が東京の出版社に勤めていたことがあると聞きつけたようだった。渡されたメモ帳を読んでみて驚いた。文字がぎっしり並んでいる中に、霊や神話に出てくるような神が登場し、おまえは救いようのないやつだと叫んでいる。まるで戦記小説だった。
「おもしろい小説だね」。川畑が感想を伝えると竜人は表情を変えてこういった。
「いえ、これはノンフィクションです。本当に起こったことです。しっかり読んでください」
川畑は、はっとした。ああ、そうか。皮膚が溶けたり、脳みそにガンガン釘を打たれたりする。これが患者の現実なんだ──。長い間病院に勤めてきたのに全然わからなかった。川畑は深く反省した。
患者の情報網があるのか、竜人に続いて次々とほかの患者が文章や絵を持ってきた。どれもこれもおもしろい。川畑は胸の高まりを覚えた。図書室によくやって来る精神科医の森越まやに経緯を説明して読んでもらうと、森越は「ちょっとこれ、本になるんじゃない?」と目を輝かせた。森越の言葉が、川畑と竜人の背中を押した。本業の合間を縫って編集作業を開始した。
こうして2006年3月、竜人を編集長に迎えた「シナプスの笑い」が創刊された。巻頭に竜人による序文「気持ちだけ一騎当千」がある。
(前略)今はまだ小さいが、いずれ昇り竜となって、天を呑み込むことになるかもしれない。誰でも自分しかかけないものを持っている。それを発掘するのがこの雑誌の目的である。「精神病」の光と影を浮き彫りにする雑誌をここに創刊します。
ミステリアスな文の集団、この集団はなんなのだ。
創刊号は1500部印刷したところ、話題が話題を呼んで即座に完売。増刷して計3000部が売れた。鹿児島の繁華街、天文館にある書店ブックジャングルの店長が平台で大きく展開して応援してくれたことも力になった。
もしかして仕事になるんじゃないか。そう感じた川畑は森越と共にNPO法人、精神をつなぐラグーナを設立した。2号からは幻聴や妄想を患者の立場から説明する新企画「ノンフィクション精神科事典」が始まり、注目された。
ここまでは、患者の同人誌で終わる話かもしれない。書いたものが本になったら喜んでもらえる。売れたらうれしい。読んでもらえたらなおうれしい。それで十分という人はいるだろう。だが川畑と森越の考えは違った。
外とのつながりをもって、デイケアを一歩出よう。一冊の本で世の中を変えていこう。病の回復の先に道をつくろう。
「仕事としてできるよ」。森越は病院の仕事と編集の二足のわらじをうしろめたく感じていた川畑を決意させた。
とはいえ、会社をつくる方法などまったくわからない。二人はノウハウ本を読み、手探りで準備を進めた。A型事業所に必要な職業指導員や生活指導員も確保し、2008年2月、株式会社ラグーナ出版が誕生した。
翌年、ハローワークで社員を募集すると応募者が殺到し、その日のうちに告知を終了せざるをえなかった。働きたい人がこんなにいるのか──、二人は確かな手応えを感じた。

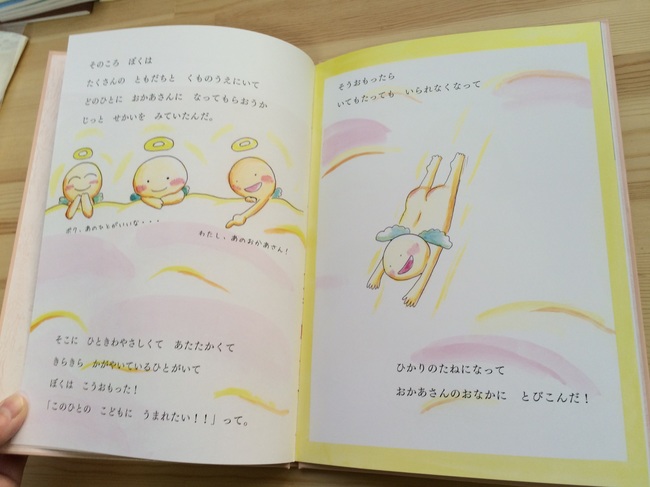
働くということ
アパートの小さな編集室から始まったラグーナ出版はその後、自立訓練事業所ラグーナを併設し、現在はオフィスビルのワンフロアを占める規模になっている。
労働時間は多様である。午前9時から午後4時までの人、5時までの人、午前中だけ、午後だけの人もいる。一人一日あたりの介護報酬5200円から家賃や諸経費、紙代などの原材料費、スタッフの人件費がまかなわれる。患者への給料は売り上げから支払うことが決められており、週に35時間働けば14万円+諸手当、パート社員は時給700円(鹿児島の平均時給は694円)。そこに障害年金が加わる。売り上げだけで当事者の給料をまかなえるようになったのは、会社設立4年目の2012年からだ。
入社8年になるベテラン編集者の星礼菜は、退院後はカーテンの縫製や事務作業をしていたが、ラグーナに入社後は編集作業のほかに大学美術科出身の腕を生かしてイラストも担当している。デザイン班の綾はライトノベルの賞を受賞した小説家でもあり、日に3〜5枚のノルマを課して執筆を続けている。
本をつくるとはどういうことか。そんな問いに、編集部員の一人、織田士郎は、「出版物に対する責任をもつようにさせます」と答えた。
病を患う前、織田は新聞社の社会部記者だった。退院後は弁当屋で働くが自分にはどうも向かない。悩んでいたところで出会ったのがラグーナ出版だった。英国留学で培った英語力を生かして翻訳に携わり、私が話を聞いた時には、オーストラリアの国家的プロジェクトとして実施されている包括的な学校精神保健プログラム「マインド・マターズ」の翻訳を終え、DSM診断の教科書を訳しているところだった。DSMとはアメリカ精神医学会が刊行する「精神障害の診断と統計マニュアル」で、世界的にも使用されている精神科医のためのガイドである。
私は彼らの仕事の質の高さに圧倒された。考えてみれば、精神疾患は誰でもかかりうる。サラリーマンも、作家も、スポーツ選手も、学校の先生もかかりうる。ところがいったん病気になると、退院後に働ける場所は一様で限られてしまう。個性を発揮する場面は少なく、世の中との接点が少ないルーティンの作業がほとんどだ。
川畑と森越の問題意識はそこにあった。社会の中で働くことにこそ精神疾患の回復の鍵がある。働く喜びを実感できる仕事してほしい。彼らのつくる雑誌や本を病院や地域で暮らす患者の枕元に届けたい。そして、患者が表現する場を提供したい。竜人が願ったように、「昇り竜となって天を呑み込む日」を目指して。
みな口々に、働き始めてから精神的に強くなったといい、出版に携わる者として、価値あるものを未来に残さないといけないという使命感をもつようになったという。
「シナプスの笑い」の編集方針である「『シナプスの笑い』が伝えたい十のこと」第十条には「最後まで生き抜くこと」とある。心の病を通して見えるものはまだまだある。内なるマグマを抱えたミステリアスな人々の挑戦は続く。

