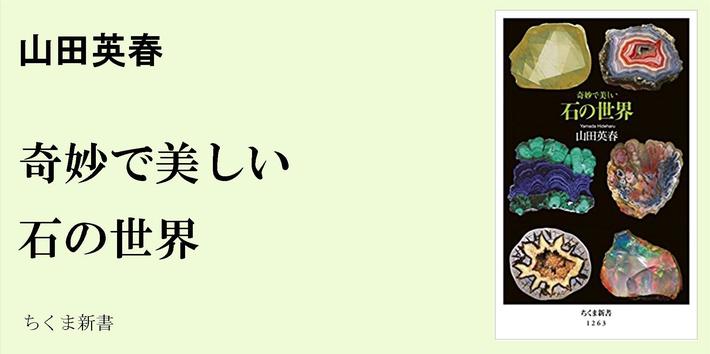18世紀後半に入り、化石がまぎれもなく生物由来であることが、顕微鏡による観察などで裏付けられるようになってもなお、化石に関する書籍にパエジナが登場することがあった。石の中に見える「絵」には生物由来のものと、そうではないものとがあることをはっきりと示すことが議論の出発点として必要だったからだ。化石をめぐる議論において「天変地異論」に対して新たに生物の変移、進化という考えも登場し、もはやパエジナはそうした考察に関わるものではなくなった。
1777年に出版された、ゲオルク・ヴォルフガング・クノールとヨハン・エルンスト・ヴァルクという二人の「天変地異論者」による化石に関する書『地球がこうむってきた大異変の記念物総覧』には、パエジナについての詳細な説明のあとで、次のように書かれている。
「偶然に生まれた図像であり(中略)かつて大いに尊重されていたものだが、今日ではすっかり信望を失っている。こうした自然のたわむれも、好事家のなぐさみとしてしか通らないのである」
無機物にも生物と同じ形を与える「自然の造形力」を前提にしていた「自然のたわむれ」という言葉にも、ここではもはや、単なる偶然、という程度の意味しかあたえられていない。
「好事家」と「博物学者」の境界が曖昧だった「驚異の部屋」の時代、パエジナは世界の謎を語りえる特別な石だった。だが、「驚異の部屋」が近代的な博物館になり、地質学や古生物学など、学問の分野が細分化されていくなかで、この石の置き場所はなくなっていった。ただ、その不思議な魅力が全く人の関心をひかなくなったかといえば、そうではない。風景に「似ている」ということは、それだけで人の意識に強く訴えるものがある。パエジナの模様は20世紀に入り、芸術が西洋の伝統的な文脈から自由になると再び注目されるようになる。「好事家のなぐさみでしかない自然のたわむれ」は、とくに個人の夢想や視覚的たわむれこそを重視したシュルレアリストたちにインスピレーションを与えるものとして珍重されたのだ。