メイプルソープという特異点──80年代と90年代で写真はどう変わったか?
ここでは写真家・上田義彦とロバート・メイプルソープを軸にして、90年代から現在にいたる写真について、別の角度からRe-thinkingしたいと考えている。
今手元に、上田義彦が2015年に出版した、600ページに近い大冊写真集『A Life with Camera』があり、それを飽かず繰り返し見ている。その中には、80年代から見知った写真もあれば、たった今の新しい写真も、分け隔てなくリミックスされている。
改めて言うまでもなく上田義彦は、日本のコマーシャル写真の頂点に居続ける存在でありながら、同時に初期の『QUINAULT』(1993)『AMAGATSU』(1995)から近作の『materia』(2012)などの、野心的かつ精力的な作家活動を行い、写真集を発表し続けてきた。また自らGallery 916を、2012年から6年間にわたって運営するなど、旧来の「写真家」のモデルでは括ることのできない重要なプレイヤーである。
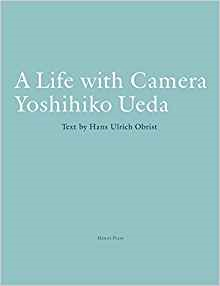
この『A Life with Camera』は、実に上田の写真の特性をよく表すものだ。なぜなら広告で撮られた有名人のポートレートも、作品として撮られたポートレート写真も「等しく」収録され、それらは何の違和感もなくエディットされているからだ。
本当は「写真」であるからには、「区別」を設定する方がおかしいのかもしれないが、「等価であること」を実証できる写真家が何人いるだろう?
僕に『A Life with Camera』を何度も飽かず繰り返し見させる「写真の力」とは何なのか。それは彼に出会った時から現在にいたるまで、僕の心を捉えるものなのだ。
モノが見える。見えるように、写真にする、その深さ。理屈や説明やあらゆる想念を剥ぎ落として、たどり着く「透明」な深さ。
それは上田義彦とメイプルソープの写真に共有の「神通力」だ。
まずは、上田義彦の写真との出会いから話しておこう。僕は1993年3月号から雑誌『コマーシャルフォト』で毎月「innovator」という特集シリーズで、広告写真家の中で、どのような変容が起こっているのかをフィールドワークする機会を与えられた。90年代初頭の、バブルによる虚栄の余韻と、その崩壊直後の混乱期。リアルのシフトの中で、最も影響が及ぶのは、あきらかに広告(写真)の分野である。
広告業界の「内部の者」でもなく、評論家を名乗ってもいない「外部の者」である僕のような存在に、資本主義表現の最前線で起こっていることをリサーチさせようとする雑誌の英断に、今さらながら驚かされるが、これは実に重要な体験だった。
最初に取り上げたのが、上田義彦だった。タイトルは「カオスへ向かう広告写真」とつけた。連載形式は、僕が写真家に徹底したロングインタビューを行い、それに基づき、彼らが撮った「広告写真」を分類・分析し、テキストを書き下ろすというものである。
人選は、僕と当時の編集長だった吉岡達夫さんとで行なったので、変容を絵に描いたような「常識的でない」面白いものになった。
ちなみにライナップを記録しておくと、次のような面々である。
高橋恭司、上田義彦、森川昇、小林和弘、高木由利子、冨士原美千代、大坂寛、白鳥真太郎、厨屋雅友、菅原一剛、小林鷹、大沢尚芳、金子親一、羽金和恭、斎門富士夫、小林響、宮本一郎、蔵田好之、長島有里枝、ホンマタカシである(単行本化するときに、十文字美信を特別に取材し、書き下ろして追加した)。
この連載を2年ほどやったある日、広告写真界の重鎮的な人と会う機会があったときに、「君の連載のおかげで、それまでの広告写真が破壊されてしまった」とイヤミを言われたことがある。今まで欧米のペン、アヴェドン、ニュートン、ウェーバーらの「モノマネ」だった広告写真が、バブル崩壊と共に崩壊したわけだが、確かにこの連載は、今見てもラディカルだったと思う。
1994年には、この連載をまとめた単行本『東京広告写真』をリトルモアから出版した。各章タイトルはこんな具合である。
広告写真の「力」をめぐる対話/広告という名のロード・ムービー/カオスへ向かう広告写真/ファッション写真の距離/浮遊する身体感覚とヌード写真/愛の写真・写真の愛/クワイエットな写真の「力」/コミュニケーションの逆説/モノへ旅する眼/逃走するポートレイト/写真と生活感の回路/ストリート・アティテュード ’90S。
ざっと見ただけでもわかってもらえると思うが、この写真変容の分析は、広告訴求のために「強く」「明解な」力、言い換えればモダンな力を要請されていた「写真」が、ポストモダン産業社会への本格的なシフトの中で発生している写真の症候群を、さまざまな角度から論証することになった。
タイトルを「東京広告写真論」にせず、「東京広告写真」にして、表紙にホンマタカシの写真を、天地逆にADの仲條正義さんにデザインしてもらったのも、モダンな傍観者の論ではなく、写真病にかかった当事者として、自らをサラシ物にしたいと思ったからだった。
また、重要なのは、1998年の4月に『コマーシャルフォト』の別冊として『上田義彦・広告写真』をまるまる1冊編集したことだった。『コマーシャルフォト』での上田義彦特集をさらに拡張したもので、巻末には上田義彦と後藤繁雄のロング対談も収録されている。
2人の議論の中心には「写真の力」がどこから来るのか、という解き難い謎があり、その特異点としてロバート・メイプルソープの写真が横たわっているという共通の認識が強くあった。90年代の写真にシフトするには、メイプルソープの写真との格闘なしにはありえないと思ったのだ。
『コマーシャルフォト』1993年の上田義彦特集号で僕が書いた記事の一部を、まずはここに転載する。
この章タイトルは「メイプルソープの死によって、80年代は終わり90年代は始まる」というものであった。
「ズボンから飛び出た巨大なペニスも、ムチを肛門につっこんだポートレイトも、女ボディビルダーの肉体も、黒バックに宙に浮くように撮られた女性の頭も、白いキャンバスの上にプラチナプリントされたアポロも──それらは同じことを語る。「明らかな写真」はタブーや物語や、批評言語や、意味解釈など入る余地がないということを。全ては終わってしまい、ここには写真があるだけなのだということを。「明らかな写真」があるだけなのだ。「良く写るモノ」を撮ってできあがった写真があるということなのだ。それ以外にはもう何もない世界。私たちはそんなところにいる。
彼(上田義彦)はメイプルソープの肖像を撮る。それは彼に「写真」を確認させる。それは結果的に彼に「時代の写真」を教える。彼はその写真の作法で広告写真も撮る。
僕と彼は死んだメイプルソープを撮ることを喋り合う。そしてエイズの人々を撮ることを喋り合う。『遺品』を撮ること、人のいない部屋を撮ること……。エイズが出現した前と、出現したあとでは写真はどう違うのだろうか? メイプルソープの「透明」へ向かい、そこから90年代の写真を始めること。
後藤 メイプルソープは死んでしまったけど彼をまだ撮り続けることってできないものですか。
上田 撮ると言うのは?
後藤 メイプルソープをまだ撮るということですよ。使っていた部屋とか……。
上田 ああ、そういう意味ですか。
後藤 カメラでも、椅子でもボールペンでも、着ていたシャツとか……。
上田 1989年の3月10日でした。僕がサントリーの仕事でレイ・チャールズを撮るため、ニューヨークについた日の夜、新聞で彼が亡くなったのを知りました。とてもショックでした。出会いと別れの不思議を思いました。葬儀の日、僕は撮影をしていたのですが、知人にたくして彼が好きだったランの花を贈りました。僕は最初メイプルソープのことが本当に大嫌いだったんです。ところが本人に会って、初めて何か解ったような気がしたんです。あっ撮りたいと思いました。カメラの前に座ってもらったときにこの人はなんて写真を知っている人なんだろうかと思ったんです。
後藤 撮影できたんですね。
上田 そうです。それからもう一度、写真を見直したんです。
後藤 そのときはエイズって知ってたんですか?。
上田 いや、まだ知りませんでした。直後にエイズというのがわかって、彼の写真はまた少しずつ変わってゆきました。亡くなってから、あの人が見たことを自分は理解できたような気がしました。このまま、あの人がつくってきた写真が死ぬまでに見えてきて、未完に終わっている写真がどうなってゆくのかなと思うんです。メイプルソープは死にましたが、彼のやろうとした写真が死んだわけではないんです。
後藤 今は時代の先が見えないってこともあって、カメラマンはニュートンとかアベドンとか50年代の写真スタイルをもう一度鏡にして次のことを考えているでしょ。ところがメイプルソープは今、回顧展が開かれて、スキャンダラスな側面とか、その反面で写真史的に歴史化されようとしているけれど、メイプルソープの写真が何故出てきたのか、写真の質とか意外と把まれてないような気がすごくするんです。誰も彼の写真の本当のすごさを語っていないように思えてならない……。
上田 きっと、メイプルソープ以前と以後では写真というものの世界が違うと思うんです。それぐらい大きなものだと思います。彼の写真はまだ終わってないんです。メイプルソープをまだ撮るということが写真にとって大切なことだと思うんです。
また1994年での対談でもわれわれはメイプルソープの写真について、くどいと感じるほど再度語り合っている。
上田 後藤さんと一緒に、ニューヨークにエイズの人たちのポートレイトとインタビュー、同時にメイプルソープの遺品を撮ったのも刺激的な作業でした。メイプルソープのこだわりも含めて、80年代に別れを告げた気がするんです。
後藤 メイプルソープの、生前にやった最後の写真展のタイトルは、いみじくも『パーフェクト モーメント』だったんですからね。やっぱり、僕たちの生きてる様っていうのはパーフェクトじゃないわけです。好き嫌いにかかわらず、僕らは、メイプルソープ後の時代に生き延びているわけだから。90年代に入った時、僕は、荒涼たる野に花がさいてるような世界に入ったなって思ったんです。だから、僕は僕で、上田さんとニューヨークに行ったのは、すごく大切な区切りだし、写真的体験でもあったんですよ。もっと、はかないけど、スウィートな方へ脱出したかったんですね。
上田 自分の生活も変わったし、身の回りのことをちゃんと見ないとっていう方向に進んで行きましたね。
後藤 メイプルソープは、80年代のヴァニティライフと写真のオブセッションによって一種戦死したんだと思うんです。日本でもバブルが崩壊して広告写真も様変わりしました。写真の中に、今言った、日常生活的な触覚、「私的」な感覚、リアリティーが入り込んできたと思うんです。この間の写真ブームは、人々のコミュニケーション感覚の変容に対応した90年代を象徴する事件だと思うんですね。
その後も、ここで提起された「メイプルソープは死んだけれど、彼のやろうとした写真はまだ終わっていない」という彼がかけた魔法(写真の呪い)は、2018年の現在に至るまで、我々が対話するたびに、語ることになる「反復される問い」となった。
次に、われわれのメイプルソープへのアプローチの日々を振り返ってみたい。
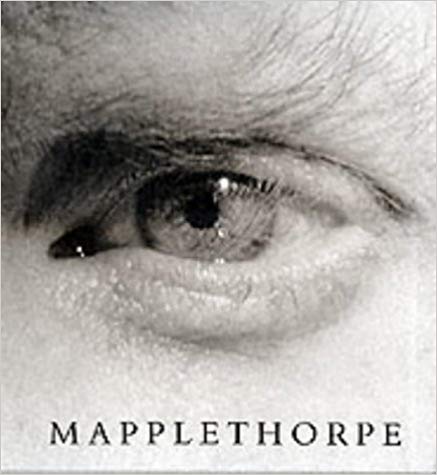
「メイプルソープの写真は終わっていない」
僕の企画案は、エイズの取材とリンクさせて、メイプルソープの遺品や墓、そして彼が撮影したモデルを上田義彦が再び撮影し、「成仏させること」だった。リプレイとビヨンドである。
メイプルソープの遺品がどのようなものであったかは、1989年10月31日にニューヨークのクリスティーズで、ロバート・メイプルソープ財団によって行われたベネフィット・オークションのカタログにおいて、全て見ることができる。
そのカタログの巻頭には、生前メイプルソープがどのようにコレクションした作品や花瓶、オブジェ、他者の写真と共に暮らしていたかという、彼の部屋の写真も収録されている。
僕は事前に、財団に連絡をとり、オークションによってそのコレクションを、現在持っている人を突き止めて、取材を申し込む手はずを取ったのだ。
メイプルソープは、悪魔的であり、それをきわめることで、天使的な、類まれなる力を獲得する回路を発見した写真家だったと僕は思う。初期に彼がつくっていたオブジェにはその呪物性が露出しているし、その悪魔性の転調を導いたのがパティ・スミスだったのだろう。
まずは撮影の日々の日記を抜粋しておきたい。ナン・ゴールディンの回でも書いたように、このエイズの取材は、YMO再生のプロジェクトと同時に行われている。「死」と「再生」のカオスが、高速で渦巻く中で思考・作業が行われていたのだと思う。それは僕たちにとり、新たな旅立ちに不可欠な儀式でもあった。
ニューヨーク日記
1993年2月17日
UAの朝一番の便でロサンゼルスからニューヨークへ。パラマウント・ホテルへ到着するとジェニー・ホルツァーのスケジュールが変更になり、突如今日はオフとなる。YMOがレコーディングしているスカイライン・スタジオに連絡し、彼らのインタビューに変更。夜遅くまでスタジオ。細野さんのメモをもらう。再生アルバムのテーマが「ハイテック・ヒッピー」になったことを知る。
2月18日
朝11時、ハリー・ランのアパートメント再訪。15時、パラマウント・ホテルの2Fでバーバラ・クルーガーにインタビュー。「ボディとパワー」について。同時にYMOの本のブックデザインも依頼。夕方、ダンジガー・ギャラリーで、買いそびれていたメイプルソープ撮影のヤン・ファーブルの本を買う。
2月19日
朝、11時。MoMAの教育部長、フィリップ・ヤノウィンの家へ。本棚には先日ドイツで出たばかりのナン・ゴールディンの新しい写真集(『ジ・アザー・サイド』)。彼は多忙で疲れているが熱弁。クリントン時代の希望。昼1時にエド・マキシーのアパートメントへ行く。カセットを使わないでインタビュー。随分長く話をする。メイプルソープの遺骨が納められた墓の撮影のOKをもらう。夜、ウエストベリー・ホテルでホルツァーに逢う。コメントをもらう。すばらしい顔をしている。カメラマンがいないのが残念。8時頃、坂本・細野・高橋のYMOのメンバーが合流。彼女に再生アルバムのジャケットを依頼。『トゥルーイズム』をアレンジしたジャケット制作OKとなる。デザインはMカンパニーのティボー・カルマンを指名。
2月20日
朝7時30分より、ブライアン・ワイルとロケバスに乗ってサウスブロンクスのニードル・エクスチェンジを見にいく。ニードル・エクスチェンジとは、麻薬中毒の人々から他者への感染を防ぐために、新しい針を配布するという運動。サウスブロンクスは、ビルが瓦礫のように崩壊し、空き地には紙くずが舞い、無人都市のようだ。まるで戦下のベイルートの光景に見える。内乱都市。ハーレムへ。ロス・ブレックナーがキャンセルになったので、ゆっくりと昼食。スカイライン・スタジオへ行き、YMOのインタビューを続ける。
2月21日
朝、メイプルソープの原稿など再構成。昼、ホテルでナン・ゴールディンに逢う。打ち合わせとインタビュー。YMO写真集の撮影依頼。エイズで死んだ友人を撮った写真集『クッキー・ミュラー』くれる。彼女が撮ったデビッド・ヴォイナロヴィッチの話、ベルリン生活の話。ナンを連れてスカイライン・スタジオへ行き、坂本さんに紹介。今日はYMOはお休み。坂本さんにインタビュー。夜、ポーラ・クーパー・ギャラリーでアンドレ・セラノの新作『モルグ』を観る。素晴らしい。恐怖とエクスタシー。タブーと快楽。死と美。上田義彦、高熱をおして1月にひき続き到着。
2月22日
朝、10時よりPWACの部屋でエイズとHIV感染者のインタビューと撮影。途中、メイプルソープのモデルだったケン・ムーディーがやってきて撮影。
2月23日
朝からGMHCの地下の部屋でエイズとHIV感染者のインタビューと撮影。2時、ナンとYMOのメンバーを引きあわせる。夕方6thアヴェニューにあるマイケル・スタウト(ロバート・メイプルソープ財団の会長)のオフィスを訪ねる。オフィスが2面が窓でセントラル・パークが見える。
2月24日
朝、モーメンタム・プロジェクトでエイズとHIV感染者のインタビューと撮影。1時にダグラス・クリンプ訪問。『エイズ・デモ・グラフィックス』。上田義彦と共に、メイプルソープの墓の撮影。夜、パラマウント・ホテルでケン・ムーディーにインタビュー。
2月25日
朝、GMHCにてインタビューと撮影。夜、ロバート・ミラー・ギャラリーへ。彼の妻の父が急死のため、インタビューを見合わせる。9時に僕が泊っているパラマウント・ホテルに坂本さんが来てくれる。
2月26日
朝9時にホテルを出てタクシーで写真家デュアン・マイケルズの家へ。イーストの古いレジデンスの玄関でマチスに似た初老の男が迎えてくれる。地下に案内されて僕は待つ。エイズの話、写真の話、モランディの話。彼は自分の詩を朗読してくれる。10時30分、今度はローリー・シモンズのアトリエに行く。広いモダンなスタジオには彼女の有名なデコレーション・ケーキ人間のモノクロ紙焼きが貼ってある。エイズで死んだジミー・デ・サナの話をする。午後、「クリエイティブ・タイム」へ行き、MTVでボツになったディー・ライトのキアーの出ているアボーションに反対するビデオなどを見る。夜、「グループ・マテリアル」のジュリーの家に行く。夫であるセラノが帰り際に来る。道で彼と別れて、歩いていると、今度はメイプルソープの元マネージャーで、今はブライアン・ワイルの展覧会などの仕切りをやっているティナ・サマリンとばったり逢う。
マイケル・スタウト、ドミトリー・リーヴァス、リン・デイヴィス、ティナ・サマリンらロバートのことをよく知る財団メンバー。プリンターのトム・バリル、友人のスティーブン・シェイ、モデルをつとめたケン・ムーディー、ロバートの弟で写真家のエド・マキシー、そしてフォトディーラーの大物で、メイプルソープのスキャンダラスなボックスセット「The X, Y, Z Portfolios」を共同発行したハリー・ラン。彼らのレジデンスを僕と上田義彦は訪ねてまわり、インタビューと撮影を続けた。その撮影の全てが「写真と宿命」を考える上で、極めて印象的な体験の連続だった。とりわけシェイが譲り受けた「蛇」、ハリー・ランが所有していた「笑うサチュロスの像」は忘れがたい。
これらの取材は、日本船舶振興会がエイズ支援のために発行した『Together』誌のためのものだったが、取材をつづけるうちに、これはメイプルソープについての、本をまとめなければならないな、という気持ちが固まって一気に長文を執筆した(この本もまた未刊だが、テキストもほぼ出来ており、出版の計画は、今もまだ諦めていない。この時期パティ・スミスは一切のインタビューをしておらず、それもあってずっと時期を計っている間に、二十数年間がたってしまったのが正直なところだ)。
その未刊の原稿の中から、僕と上田義彦がどのようにメイプルソープの写真についてアプローチしたかを物語る、当時書いたテキストの一節を抜粋しよう。
ロバートが飼っていた蛇を譲り受けたスティーブン・シェイの家での撮影の時の話。
僕と上田義彦は喋りあう。エイズにかかった人々を撮ることを喋りあう。メイプルソープの『遺品』を撮ることを喋りあう。解決することは出来ないにしても、エイズが出現した前と後とでは写真はどう違うのかという問いをめぐって喋りあった。
上田義彦は1986年ニューヨークでメイプルソープのポートレイトを撮ったことがある。
「僕は最初メイプルソープのことが本当に大嫌いだったんです。ところが本人に会って、初めて何かわかったような気がしたんです。あっ、撮りたいと思いました。カメラの前に座ってもらった時に、この人はなんて写真を知っている人なんだろうかと思ったんです」
上田義彦は言葉を丁寧に探しながら喋る。
「その時はエイズって彼は知ってたんでしょうか?」
「いや、まだ知りませんでした。直後にエイズということがわかって、彼の写真はまた少しずつ変わってゆきました。このまま、あの人が作ってきた写真が、死ぬまでに見えてきて、未完に終わっている写真がどうなってゆくのかなと自分でも少し思ったことがあります。彼は最後に、ものすごく“透明な写真”にたどりついたと思うんです。彼が死んでその“透明な写真”ということがどうなるのかなと思います。メイプルソープは死にましたが、彼のやろうとしていた写真が死んだわけではないんです。きっとメイプルソープ以前と以後では写真というものの世界が違うと思うんです。それぐらい大きなものだと思います……」
温室の中にセッティングした黒いバック紙の上で、枯れ木にからまったオレンジ色の「ロビー」はストロボの光を浴びる。手に持って抱くと、その蛇は冷たく、「生きている宝石」という言葉がこれ以上ぴったりくるような生き物は他にないと僕は思った。シェイはロバートが死んでから3年の間、この蛇を学校に持って行き大勢の子供たちに見せたり、触らせたりした。「子供はちっとも恐がらないのさ」と彼は笑う。
ロビーはフラッシュを浴びても驚かず、悠々とポーズを変える。シェイがいうように、この蛇はカメラマンがとり憑いたモノだから、「ベリー・ナイス・サブジェクト」に違いないのだ。撮影をしながら僕たちは、メイプルソープが「選んだモノ」の力を実感しはじめる。メイプルソープの写真は、写真とモチーフの特別な相乗的な力によって他に類のないものになっていったことが実感されるのだ。
上田義彦はシャッターを切り続ける。ロビーは写真を誘惑し続けている。
エイズに冒された最期の日々
ロバート・メイプルソープは1989年、つまり90年代を待たずして死んだ。彼の最期の日々はこんな風に過ぎて行った。
● 1986年の9月、肺疾患(P・C・Pカリニ肺炎)のために入院、エイズと診断される。
● 1987年1月14日 ボーイフレンドであったキュレーターでコレクターのサム・ワグスタッフ、エイズにより死去。
● 1988年初めより病状悪化。夏には2度、セント・ビンセント・ホスピタルに入院。5月27日、メイプルソープ財団設立。エイズ治療と研究への資金援助と、写真芸術の発展のための助成を目的とする。この年、ホイットニー美術館、ロバート・ミラー・ギャラリーで個展。そして生前最後となる個展「The Perfect Moment」がフィラデルフィアのInstitute of Contemporary Artで開催される。
● 1989年2月、セント・ビンセント・ホスピタルに再入院。『ヴァニティ・フェア』2月号に「Robert Mapplethorpe’s Proud Finale」掲載。彼のエイズ症状がマスコミを騒がせる。3月1日、CD4治療を受けるためにボストンのニューイングランド・ディコネス・ホスピタルに入院。しかし症状が重すぎ治療を断念。3月9日、午前6時頃同病院にて死去。3月14日、クイーンズ区のフローラルパークのOur Lady of the Snow教会で葬儀が行われる。
死は誰にでもやってくる。しかしメイプルソープの死は、あまりにも凄絶であり、写真を通した「永遠性」、それは名誉や栄達とも結びついていたように思われる。
ロバートのマネージャーだったティナ・サマリンは、「『ヴァニティ・フェア』の記事の書き方はスキャンダラスなものだった。ロバートはその『Proud Finale』というタイトルにひどく怒っていた。協力してきた人間をそういう扱い方するなんて。でも、逆にその記事によって信じられないほどのスピードで、全ての作品が次から次へと売れて行った。『ニューズウィーク』が彼がエイズであることを書き、彼の病気は一般的に知られ、人々は争うように彼の写真を買いたいと言って電話をかけてきた」と語ってくれた。
『ヴァニティ・フェア』の誌面には、エイズの重い症状のメイプルソープの姿が掲載された。しかし彼は、死という現実を受け入れず、直面する事実を拒否し、最後まで、写真を撮り続けようとした。
スティーブン・シェイは、メイプルソープの死に最後まで立ち会った1人だ。僕のインタビューに、こう語ってくれた。
「ホイットニー美術館で彼の回顧展が開かれた時、彼は車椅子でオープニングに現れ、人々を驚かせた。そして、死ぬ1ヵ月前にニューヨーク近代美術館でやったアンディ・ウォーホル回顧展に行ったときも車椅子に乗っていた。車椅子は外に出かけるときだけで、アパートでは歩きまわっていた。でも、エイズの合併症によって神経障害はすごく痛ましかった。熱も出たが、神経障害のせいであまり感じなかった。
ボストンの病院に行くとき、彼はもう飛行機に乗れるような状態ではなかったから、大きなワゴン車で連れて行かねばならなかった。これが最後の治療のチャンスだと思っていたのに医者は彼を診て、治療しても無駄だと言った。ロバートは死ぬ前日、ベッドに座って自分の名前をサインし続けていたそうだ。ただ紙にひたすらサインし続けていたのだ。彼は先に予定されている展覧会のことが心残りで死ねなかった。
ロバートが危篤だという連絡が、ごく親しい友人の所に来た。医師はみんなに夕方の5時半に来るように言った。みんなは集まった。その中で彼は最期のときを迎えようとしたのだけれど、彼はまだ死ななかった。意識はないのだけれど、彼はまだ生き続けていた。次の日の朝まで何時間も彼は死なずにいた。ロバートは10時間も闘い続けた。看護師がロバートを抱えて言った。
『さあ、ロバート。行かせなさい、解放してあげなさい。あの光を見なさい、天国の光を見なさい。行きなさい』
でもロバートは行こうとしなかった。彼の目には「怒り」が見えただろう。彼は『僕は死なない。死なないんだ』と訴えていた。彼は回復することなく、その病院で死んだ」
上田義彦の眼差し──メイプルソープの問いに対する答え(2015年4月2日 Gallery 916での対話)
メイプルソープが仕掛けた写真の問い。それは、「決定的瞬間」でもなく、「写真の真実」でもなく、写真を限りなく透明にすることにより得られる死を超えた「永遠性」のようなものであり、それは写真というメディアに内在する「可能性とは何か?」を問うこと、と言い換えることもできるだろう。
いや、写真が病として持つ、「パーフェクション」という名の「不可能性」の呪縛と言ってもよいだろうか。
ともあれ90年代の「問い」を引きずりながら、僕たちは、「メイプルソープ後」の写真世界を生きることとなった。
2008年に、僕はG/P galleryというギャラリーを恵比寿に開廊することを決意した。そして、所属アーティストラインナップを考えたときに、すぐに声をかけたのが上田義彦であり、第1回の展覧会は上田義彦個展「骨と石器」であった(それ以降、G/P galleryは上田義彦のマザーギャラリー的な存在として、2009年「QUINAULT」、2010年「YUME/MYANMER」、2011年「静まる」などの個展を開催することになる)。
上田義彦から始めようと思ったのは、2006年に国際写真フェアParis Photoを見に行った際(このときの特集が「北欧」であり、またハリー・ランへのオマージュの年に当たった)、「ここに出品して、戦える強度を持ち、なおかつユニーネスをもつ写真は何だろう」と考えたときに、すぐに上田義彦の2つの作品集『QUINAULT』『AMAGATSU』が浮かんだからであった。そこにある「アニミズム」と「東洋的なカラッポな身体性」ゆえにである。
従来の写真史のコンテクスト上にいる作家ではなく、資本主義のイメージ生成の渦の中から生まれたコンテンポラリーな写真作家を、あえて選択すること。それは、重要な批評的な姿勢であり、挑戦すべきことだと僕には思われた。
G/P galleryを開廊したばかりの2008年、2009年に、幸運にもParis Photoに出展を果たせた折にも、上田義彦と若手作家を出品して評判を得たし、海外のギャラリーから引き合いが続いた(これ以降、上田義彦は、ロンドンの名門MICHAEL HOPPEN GALLERYで個展を開催することになる)。
また、上田義彦がGallery 916を2012年に開廊してからも協力関係は続き、2014年に開催された上田の2つの個展「M.River」「M.Ganges」に対するテキストも執筆するなど、つねに並走し続けてきた。
展覧会でのトークは、いつも印象的なのだが、2015年の個展「A Life with Camera」はひときわ重要な体験だった。
冒頭に書いたが、写真集『A Life with Camera』は600ページもの大冊であり、上田義彦の30数年にわたる写真がセレクトされている。これは自らの写真を2015年において再編・再生させる作業であった。彼は自らのテキスト「そしてまだ見ぬ写真へ」の中で、再編の作業の中で「写真とは、眼差しのことだ」と改めて気づき「眼差しを変えずにもち続けた事に誇りをかんじる。(中略)写真に逢えてとても嬉しい。写真と共に歩む人生を選んで幸運だったと思う」と心情を吐露している。
この発言を、能天気な発言だというのはあまりにシニカルだろう。
僕はトークの30分前に会場に着いた。あらかじめ写真集は見ていたが、広いGallery 916には、大小さまざまにフレーミングされた写真が、まるで記憶の群島のように寄り集まり、構成されていた。時空や事情を剥奪されて、イメージの内在性の引力だけにしたがってそれらは構成されていた。
見ていた僕は正直、とても気持ちよくなり、笑ってしまっていた。
対話が始まり僕が第一声で、「なんか本当に楽しい感じがする。写真って夢なんだなって思わせてくれます」と言ったら、上田さんがすぐに「どんな夢なんですか?」と聞くから、「広告とか作品とか関係なく、イメージが光輝いてる。気持ちよくなるんだよね」と言ったら「あー、嬉しい」と上田さんが笑った。「体系化とか理屈じゃなくて、1枚の写真があると磁石のようにくっついてくるんですよ。まったく事前に、こうしようとは思ってなかったんですけどね」。上田さんは、どのようにエディットが進んでいったかを話した。
「コトバだと陳腐になっちゃうけど、どうしようもなく嬉しくてシャッターを押しているだけなんです。こんなに気持ちよくさせてくれてありがとう、というか、嬉しさの塊。そういうのの全部だと思います」
上田さんは、本当に嬉しそうだった。写真が好きだという初心が起動させ続けてきた「旅」が、たまたま広告と出会わせてくれたり、多くの被写体と出会わせてくれたりしてきたことを、喜びをもって語り続けている。対話の時間は、あっという間に過ぎた。
そして僕もまた、やっとその幸福な対話のさ中にわかったのだ。
僕たちが、いつの間にか、ロバート・メイプルソープの呪縛から、抜け出た場所にたどり着いてしまっているということを。

